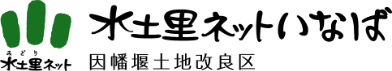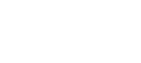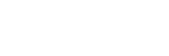日頃から本区の運営並びに事業推進に対しまして、格別のご理解とご支援を賜りここに厚く御礼申し上げます。
さて、一昨年7月の大雨による災害から、昨年は記録的高温と少雨に見舞われるなど、近年このように単に異常気象としてはかたづけられない気候が恒常化しつつあることについては、防災・減災としての観点からも治水対策同様に渇水対策もその重要性が高まっており、そこで政府は「流域総合水管理」の考え方による流域マネジメントを推進していくとしておりますが、これは治水対策としての頻発する豪雨災害とそれに伴う洪水被害の最小化を図るとともに、一方で渇水対策としての適応策となる効率的な水利用や新たなエネルギー化を図るなど、このように治水としての機能強化と安定した水供給の確保を果たせるようにするため、流域のあらゆる関係者が一緒になって、その地域の健全な水循環の確保に取り組もうとするものです。このような中で、特に農業の持つ多面的機能に代表される田んぼダムの取組は脚光を浴びており、この取組をとおしては、地域における農業の持続可能性とともに、農家がその地域においてこれまで果たしてきた役割とその必要性について、再認識いただく絶好の機会にもなっております。
既に本区では、管内の保全組織であるいなばエコフィールド協議会との連携強化を図る過程で、平成24年度よりいち早く田んぼダムの取組を決定し、その目標を1,180ヘクタールと掲げスタートさせました。この取組も現在1,079ヘクタール(目標91%達成)まで広がり、これは山形県内でもトップの取組実績が示すように、このような先進的活動に対して臆することなくチャレンジしてきました本地域農家の姿勢とその意志を誇らしく感じているところであり、あらためて関係各位に対しまして衷心より敬意と感謝を申し上げるところです。
現在農村では、農家の急激な減少に伴い一経営体の規模も拡大し、農地を適切に維持管理し続けることは簡単ではありませんが、そのような中にあっても田んぼダムの取組も含めて、いつ起こるかわからない自然災害への備えやその対応策を講ずることは極めて重要です。日頃からもっと住民自らが地域や環境に関心を持つことと同時に、他人事の意識を捨て自分事として捉えて行動に移さなければ、ここの環境は守れないと気づかなければなりません「もう考え悩んでいる時ではない」「考えるよりまず動け」と時代が求めているのです。この国の未来と安心安全な社会は、すべて行政や人任せではなく、それぞれそこで生きているものの責任と行動に懸かっていること、無関心こそが最大の敵であることを理解し、地域に興味を持って積極的に関わっていこうとする姿勢にこそ、地域課題の解決策と持続可能な社会への答えがあります。
本区はこれまで、その答えを探す過程において、一般住民を対象とした田んぼの学校(農業体験)や児童生徒を対象とした総合学習(生きもの調査/出前教室)など、様々なアプローチから地域の貢献に繋がる活動を行っており、令和5年度からは流域治水サポーターとして認定を受けながら、田んぼダムの取組の普及と推進に傾注してまいりましたが、いよいよ昨年7月23日には鶴岡市より水防協力団体としての指定を受けたことから、その翌8月2日には本区初となる水防活動として、多くの住民とボランティアの協力のもと災害時に後方支援となる土のうの袋詰めのほか、土のうステーションまでの運搬とそこでは土のうの管理と搬出を容易にするためにパレットとトンパック(いなば水防資材/表示)を用意し、それぞれトンパックには100袋の袋詰めを行いました。これは地域で発生する水害への備えとしての第一歩であり、これからも継続的にこの活動を行うことによって、突発的な災害に対してスムーズな土のうの供給を図ることを目的としているものでありますが、このストック数には限りがありますので、先ずは地域住人の生命と財産を守ることを優先とし、その緊急性や防災・減災効果など総合的に判断しながら、地域の要請に応えていく所存でございますので、この土のうステーションの土のうの活用にあたっては、鶴岡市藤島庁舎または本区まで連絡とご相談のうえ、適切な対応をいただきますようご協力をお願いいたします。
最後になりますが、今後も新たな地域づくりや未来農業を見据え、その時代に新たな価値を生み出せるよう組合員の負担軽減と生活向上に常に意識を高めながら、これからも農村振興はもとより地域防災の一翼を担っていけるよう精励する所存でございますので、関係各位並びに地域の皆さまにおかれましては、これまで同様忌憚のないご意見とご指導ご支援を賜りますよう重ねてお願いし、挨拶に代えさせていただきます。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。